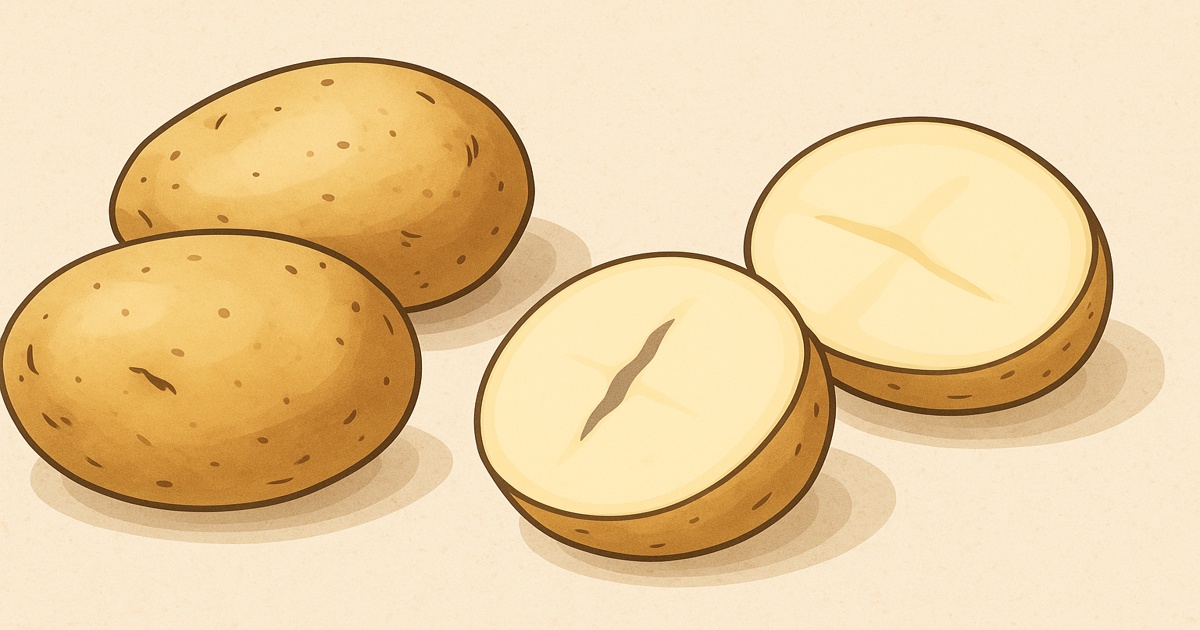料理中、じゃがいもを切った瞬間に見える黒い筋や斑点。
表面はきれいなのに、なかから想定外の色が現れると、思わず手が止まってしまいますよね。
「これ、腐ってるのかな?」
「黒い部分って食べても平気なの?」
そんなふうに感じた経験、きっと多くの方にあるはずです。
とくに、小さなお子さんやご年配の方の食事を用意しているときには、少しの変色でも不安になってしまいますよね。
自分自身もけっこう心配するほうなので、そうした不安、よくわかります。
でも実は、じゃがいもの中が黒っぽくなる現象には、いくつかの種類があるんですよ。
すべてが腐っているわけではなく、原因と状態をきちんと見極めることで、安全に使い分けることができます。
この記事では、じゃがいもの中の黒い部分にまつわる知識を、できるだけわかりやすく整理してお伝えします。
食べても大丈夫な黒さと、避けたほうがいい黒さ。その見分け方や対処法を、五感で確認できるポイントとともに解説していきますね。
じゃがいもの中が黒くなる3つの原因とは?変色のしくみを解説
じゃがいもの中に現れる黒い筋や斑点。
実はその正体には、大きく分けて3つの異なるタイプがあります。
1つ目は、ポリフェノールの酸化による変色。
じゃがいもにはりんごやナスと同じように、ポリフェノールという成分が含まれていて、皮をむいたり切ったりしたときに空気と触れることで酸化し、黒っぽくなることがあります。
とくに、内側に傷がついた部分やストレスがかかった箇所は、変色しやすい傾向があります。
この酸化変色は、衛生的にはまったく問題なく、気になる部分を少し切り取るだけで、安心して使うことができます。
2つ目は、黒変症(こくへんしょう)と呼ばれる現象です。
これは主に収穫後に低温や衝撃を受けたことで起こる生理障害のひとつ。
冷蔵庫で保存してしまったじゃがいもや、寒い時期に買ったものに多く見られます。
見た目は断面の一部にグレーや黒っぽい筋、輪っか状の模様などが出ることがあり、驚くかもしれませんが、実は加熱すれば色が和らぎ、味にもほとんど影響が出ないことが多いです。
そして3つ目が、内部褐変や芯腐れといった「食べないほうがいい変質」。
これらは高温障害・栄養不足・病気などが原因で、じゃがいもの中心部が黒く変色し、場合によってはドロッとしたり、異臭を放つケースもあります。
とくに黒さが中心から広がっていて、ぬめりや酸っぱいにおいがする場合は、食べずに処分するのが安全です。
じゃがいもの黒い筋や斑点は食べても大丈夫?見た目で判断するポイント
「見た目がちょっと気になるだけで、実は食べても問題ないのかも?」
そう思ったときに参考になるのが、じゃがいもの黒い部分の出かたと質感です。
たとえば、次のようなケースは比較的安心できます。
・じゃがいもの切った断面に、細くて浅い筋がいくつか入っている
・黒い点がぽつぽつと少しだけ広がっている
・加熱すると色がやや茶色になって落ち着く
これらは、ポリフェノールの酸化や黒変症によるものが多く、味や食感に大きな影響はありません。
一方で、食べないほうがいい状態には、共通するいくつかのサインがあります。
とくに注意したいのは、「湿り気」と「におい」です。
・じゃがいもの断面がどろっとしている
・中心部がどす黒く変質している
・明らかな異臭や発酵臭がする
こうした場合は、すでに内部から腐敗が進んでいる可能性があるため、見た目だけで判断せず、五感でしっかり確認することが大切です。
じゃがいもの黒い部分の“場所と形”でわかる食べられるかの目安
「黒い部分の出方には、どんなパターンがあるの?」
そう感じた方に向けて、じゃがいもに見られる変色の“形と位置”を知っておくと、迷いを減らせます。
たとえば、じゃがいもの皮をむいたすぐ下にぐるっと輪のように出ている黒さは、黒変症の典型的な形。
これは寒い場所で保存したときに起こりやすく、皮のすぐ内側にだけ出るのが特徴です。
また、じゃがいもの断面の内側にスジのような黒さが入っているケースでは、軽い酸化の可能性が高め。
この場合も、削るだけで取り除けるので安心です。
逆に、じゃがいもの芯に向かって黒さが集中している/ぬめりがある/においがあるといった場合は、芯腐れなどのリスクもあるため、その部分を大きめに切り落とすか、丸ごと処分する判断が求められます。
じゃがいもの黒い部分は加熱で変わる?調理方法別の変色の違い
気になる黒さがあっても、「加熱したら色が変わるかも?」と感じたことはありませんか?
実際、じゃがいもに含まれる黒っぽい色素の多くは、加熱によって変化することがあります。
とくに、ポリフェノールの酸化による変色や黒変症の場合は、加熱することで色が薄まり、目立たなくなることが多いです。
たとえば蒸したり、煮物に入れたりすれば、断面のグレーが柔らかい茶色になって目立たなくなることも。
一方で、じゃがいもの芯腐れのような傷み由来の変色は、加熱しても黒さがそのまま残ったり、逆により強く感じられたりすることがあります。
においやぬめりなども加熱では消えないため、加熱で様子を見るのはあくまで補助的な手段。
最終的な判断は、見た目とにおい、触感などを総合して行うのが安心です。
黒い部分を取り除けば使える?調理前の工夫と安全ライン
少しの黒さでじゃがいもを丸ごと捨ててしまうのはもったいない気もしますよね。
でも、焦ってそのまま使うのも不安。
そんなときは、じゃがいもの黒い部分を見極めて、丁寧に取り除くのが基本です。
目安としては、黒い筋や斑点が浅い場合は、包丁で1〜2ミリ程度削れば十分。
斑点が中心に向かって深く入り込んでいるときは、大きめに切り取るほうが安心です。
ポイントは、「切り取った断面がきれいな色になっているかどうか」。
そこまで削ってもまだ黒さが続くようであれば、その部位全体を避けたほうが無難です。
また、炒め物や揚げ物など、加熱時間が短い料理に使う場合は変色部分の残り香が出やすいため、より慎重に。
逆に、煮込み料理やポテトサラダのように火をしっかり通すレシピであれば、多少の黒さは気にせず使えることもあります。
じゃがいもの品種や保存方法によって変色リスクは変わる?
じつはじゃがいもは、品種や育った環境、保存の仕方によっても、黒さの出やすさが変わります。
たとえば、ホクホク系の男爵いもは比較的変色しやすく、収穫後の扱い方で黒変症が出やすい傾向があります。
一方、メークインなど粘質の品種はやや傷みにくいですが、長期間の保存では内部褐変を起こすこともあります。
また、保存時に冷蔵庫に入れてしまうと、低温障害で黒変症が起こりやすくなるため、風通しの良い冷暗所が基本です。
新聞紙に包んで段ボールなどに入れ、常温(13℃〜15℃程度)で管理するのがベスト。
さらに、光が当たる場所に置いておくと緑化やソラニン(有毒物質)も発生しやすくなるので、保存場所の工夫も意外と重要なんです。
安心して使うために、購入時や保存中にできること
じゃがいもの黒さを見極めるには、調理前だけでなく買うときと保存中のチェックも大切です。
購入時には、なるべく表面がなめらかで重みがあるものを選ぶと良いでしょう。
一部に黒ずみがある場合でも、それが表皮だけなのか中まで及んでいるのかは、重さや硬さである程度見分けられます。
保存中は、芽が出ていないか・においに変化がないか・表面が柔らかくなっていないかを定期的に確認。
とくに夏場は傷みやすいため、まとめ買いしたものは小分けして暗所に保管し、なるべく早めに使い切るのが安心です。
また万が一、一部が傷んでしまったときのために、他の芋に傷みが移らないよう、新聞紙やキッチンペーパーで1個ずつ包む保存方法もおすすめです。
まとめ
じゃがいもを切ったときに見える黒い筋や斑点。
こうした黒さには、酸化や黒変症などによる自然な変色もあれば、内部の傷みが進んでいるケースもあり、理由はひとつではありません。
重要なのは、見た目の色だけで判断しないこと。においや質感、加熱後の変化も含めて、総合的に見極めることが大切です。
安心して使えるかどうかを判断するには、「黒い部分が広がっていないか」「ぬめりがあるか」「異臭がするか」など、五感での確認が役立ちます。
見た目に戸惑っても、実は問題ないことも多いじゃがいもの黒さ。
日々の料理にうまく取り入れつつ、必要なときにはためらわず処分する。その見極めの感覚を少しずつ育てていけたら、より安心ですね。